
| 古九谷写 | 明末五彩磁写 | 茶陶吉崎英治の世界 |
古九谷写 |
| ●古九谷に魅せられて | |
| 今日、古九谷と呼ばれ長きに亘り人々を魅了し続けてきた日本で最初期の色絵磁器はその産地について、九谷説、伊万里説がそれぞれの論を展開してきたが、1970年以降の九谷、 有田双方における窯跡の発掘調査や史料の科学的分析法の進歩により、現在では伊万里説に議論が 収斂しつつあるようである。しかし未だ謎は多く、古九谷の全体像が解明されたわけではない。
そもそも古九谷という名称が最初に使われたのは江戸末の加賀の地であった。1800年代に入り、 再興九谷の色絵を焼く窯が金沢や南加賀に続々と誕生していた時代に、それまで加賀地方や周辺に伝来 していた国産の色絵磁器を区別する意味で古九谷としたのが始まりだったようである。そしてその 背景には1650年代に大聖寺藩が築窯し、いつしか廃窯になった九谷窯で焼かれたものがそうした伝来品だと多くの人が信じていたということがあったのではないだろうか。 さて、現代人である私たちは古九谷の伝世品を生活の中で使用することなどまずないだろう。 今、私たちが見ることのできる伝世品は大抵美術館の中に鎮座している。この白く無機質な空間は器から陰翳を剥ぎ取り、漂白してしまう。美術館という制度は展示品を権威あるものにし、ニュートラルな価値を示してくれるけれど、古い工芸品や宗教美術などにおいては、それらが本来纏っていた筈の固有の意味や奥行きを平板なものにしかねない。 |
|
古九谷における3つの様式 |
多様なデザインを持つ古九谷だが、現在は作行の特徴から祥瑞手(南京手)、五彩手、青手という 3つの様式で捉えるのが一般的である。通説に従い、古九谷は有田で焼かれたとするならば、その 制作年代は出土品の状況から、1640年代〜1670年代ということになる。 |
||||
祥瑞手(南京手)古九谷 |
 |
|||
古九谷のうちでも親しみやすく、チャーミングな表情を見せる祥瑞手は、染付と色絵の組み合わせが特徴であり、題材は花鳥、動物、人物など様々である。茶席で使われたであろう小皿類も多く、明末の景徳鎮に焼かせた色絵祥瑞の流れが窺える。 |
||||
五彩手古九谷 |
||||
平鉢類の裏面には染付文様が描かれたり、器面に染付の輪線が施されたものも少なくないが、その主役は何と言っても美しい五彩の色絵である。中国の芙蓉手の構図を基本としながら、日本的な要素を加え発展させた作品が多く、世界で最も絵画性が強調された焼物といえよう。 |
||||
 |
||||
青手古九谷 |
||||
黄と緑の強烈な色彩の対比と、力強く確かな筆捌きで描かれた主題や地紋が渾然一体となって見る者を圧倒するかのような青手古九谷。主題の輪郭が画面を区画し、その隙間を地紋で執拗に埋めていき、全体を色絵具で余白なく覆い尽くす。 |
||||
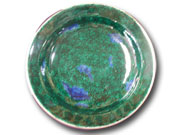 |
||||
| NEXT |